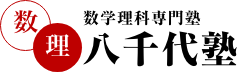小6算数データの活用⑳勉強中!


小6算数データの活用⑳勉強中!
小学6年生の保護者の方が、今の教科書を見たら、
驚かれるかもしれませんね。
「中央値とか、最頻値とかって、高校の統計学じゃなかったっけ?
しかも、選択だったから、少ししかやらなかったなー。」
という年代の方がほとんどだと思います。
しかし、現在数学教育において、統計学の占める割合は、大きくなっています。
2008年公示の中学指導要領で、中学校からで、統計学を学ぶようになりました。
2009年公示の高校指導要領で、高校での統計学が必修化されました。
現在、大学入試センター(共通テストに変更されます)では、必修問題の中でも、
出題問題数、配点ともにかなりの割合を占めます。
そして、今回の、小学指導要領で、小6から統計学を学ぶようになりました。
インターネットが普及し、コンピューターの処理速度が向上することで、
様々なデータが得られるようになりました。ビッグデータと言いますよね。
それによって、将来様々な職業において、
データを活用する力が求められるようになります。
統計学の扱いが非常に大きくなってくる、
そのため、教科書においても、統計学の扱いが大きくなっているのでしょう。
小学生に中央値や、最頻値を教えるのは、私も初めての経験でした。
とっつきにくい統計学の用語を覚えてくれるのか、
大量に足し合わせたり、ひたすら割って平均を出すなんて、
地道な作業、小学生が集中してやってくれるのか、
という心配を勝手にしていましたが、、、
実際ふたを開けてみると、ぜんぜん大丈夫でしたー!
文字が登場して、筆算の機会が減っている中学生より、
むしろ計算は早いかもしれない、なんて感じたくらいです。
ただ、小学生は覚えるのも速いけど、
忘れるのも速いので(笑)復習していきましょうね。
最後に、時間が余ったので、各自学校の単元を復習しました。
塾の授業は、先に進んじゃうので、
定期的な振り返りを大切にしましょうね。
来週までの宿題
テキストP124~125
------------------------------
仙台 数学理科専門塾 八千代塾
https://yachiyo-jyuku.com/
------------------------------
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
©2020 八千代塾